
御祭神は譽田別尊。


八幡宮社伝によりますと、天正2年に当地へ移転。慶長15年には津軽為信の参拝があったそうです。



安政2年神社書上帳によりますと創建は大同2年で、坂上田村麻呂によると伝えますが、社伝によりますと天正2年に岩木川決壊のために川岸より現在地へ移転とあります。



鶴田町誌によりますと、寛永年間に再建されており、安永3年赤田組の祈願所となり、板屋野木村宝量宮(現在の海童神社)と1年交替で神楽を奏したそう。

以下は青森県神社庁より。
『当社の縁起は甚だ古く「平城天皇大同2年に坂上田村麻呂が蝦夷退治に悪戦苦闘し同年退散せしめこの地を平定せり、依って同年9月大川畔の木を伐りて神殿を造営し蝦夷退散国中安泰守護神を勧請し、敬仰せり」とある。現在の地に遷座したのは天正2年と伝えられている。当社は安永3年、板屋野木村宝量宮(板柳町海童神社)と共に赤田組の祈願所に指定され、第7代藩主信寧公から御武運長久風雨順時五穀成就組中安全祈願の為、伊勢御田扇神宝一通太神宮大麻と鳴弦御守札が奉納され、宝量宮と1年交替で6月1日に組中でお神楽を行う事を命ぜられた。また、安永5年10月には再び藩主から太神宮大麻と鳴弦御霊札が奉納され、宝量宮と7年交替で組中で御輿を通行させるように命ぜられた。明治6年4月に村社、明治44年9月8日神饌幣帛料供進指定神社。』



本殿。



お正月には五穀豊穣を願い、鳥居に弥生画(五穀豊穣を願って額に穀物の種子を一粒ずつ貼り付けて仕上げたもの。起源は天明の大飢饉。)が奉納されます。藩政時代からの伝統が現在も息づいています。素晴らしいですね。山道闇おかみ神社にも同じく奉納されています。ちなみに1月に見逃しても道の駅つるた内にて1年間観覧できますよ。
以下のリンクから詳しく見ることができます♪

古札納所。

御祈祷受付所。

祈祷受付所と社殿の間に十和田神社が鎮座。

昭和10年旧4月19日紀年銘の社号標。

サンゴを打つ池があります。旧4月19日の祭りの日には近村の人々が参詣に来るそう。津軽富士見湖畔の戸和田神社の遥拝所とも言われているそうです。


池の畔の祠には石が祀られています。


十和田神社の横にも水神。水滸神社といい、いわゆるスイコ様のようです。

こちらも同じく昭和10年で、旧6月21日紀年銘。旧6月21日の夕方にお祭りがあるようです。

社殿挟んで十和田神社の逆側には猿田彦大神。







奉納馬。

参道補装記念碑。

広い敷地で気持ちいいですねー。




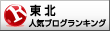
コメント